口座凍結で預金を引き出すことができない場合の対処法!口座凍結の理由とは?
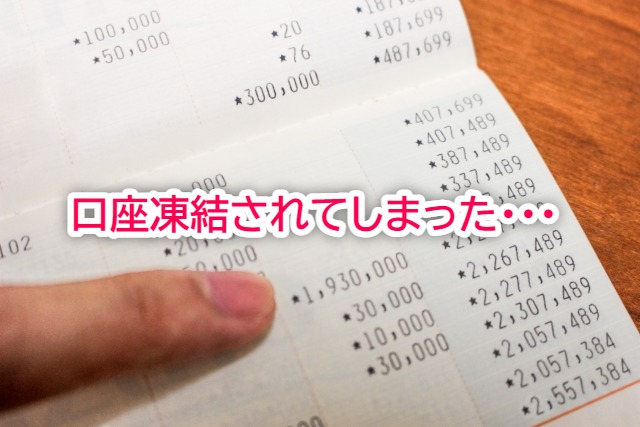
家族が亡くなってしまうと葬儀も大変ですが、役所への届出や遺産に関する問題の解決もスムーズに進めたいものです。
特に気を決たいのが金融機関による口座凍結。
口座凍結によって、
- 財産分与が進められない
- 生活費の捻出に困る
- 銀行引き落としによる支払いができない
など困ることが出てきます。
あまり経験することは無いでしょうが、口座凍結が実行される理由など普段は知り得ることはできないため、少し時間をかけて調べてみました。
簡単ですが、シェアしたいと思います。
もくじ
口座凍結とは
口座凍結とは、金融機関によって何らかの理由で、預金してある口座から、
- 現金引き出し
- 送金
- 振込
- 引き落とし
などが一切できなくなることです。
口座凍結の理由
一般的には、口座開設した本人が、
- 債務整理
- 亡くなる
- 不正利用
などによります。
似たものに「休眠預金」というものがありますが、これは10年間取引がない場合に適用され、民間での公益的な活動の支援に使われます。
口座凍結のタイミング
ちまたのウワサでは、例えば家族が亡くなってしまい、役所に死亡届を提出した瞬間あるいは翌日には口座が凍結されるという情報が出回っています。
個人情報保護の観点から役所から金融機関へ死亡届が提出されたことなど、知らされることはあり得ないことです。
もし金融機関に伝えていないのに口座凍結されていたら、他の親族が金融機関に問い合わせをしたなど、何らかのかたちで情報かせ入ってきたと考えるほうが一般的です。
どちらにしろ、死亡届の提出と口座凍結は連動していません。
口座凍結されるのはなぜか
亡き家族の口座に残っている預金などは相続の対象です。
つまり相続税の課税対象とも言えます。
自由に引き出されると、正確な相続財産の計算ができなくなり、相続税の納税にも影響が出てしまいます。
それを避けるために遺産分割協議が終わって相続内容が決定されるまで、一時的に対象口座の取引を停止するわけです。
要するに相続税逃れを防ぐという面もあるでしょう。
凍結口座の解除手続き
凍結された口座は、金融機関に口座凍結の解除手続きをすることで、取引が再開されます。
その手続きは3つのステップがあります。
- 金融機関に口座凍結解除を依頼
- 指定された書類を準備する
- 金融機関へ必要書類を提出
口座が凍結解除されるには約10営業日(暦で2週間)程度は必要です。
詳細は各金融機関に問い合わせてください。
仮払い制度
相続法改正で「仮払い制度」がスタートしたことから、上限はあるものの引き出しが可能になりました。
仮払い制度における引き出しの範囲は、
預金額の3分の1に法定相続分をかけた額(上限150万円)
です。
参考:亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?|一般社団法人 全国銀行協会
まとめ
口座凍結で預金を引き出すことができない場合の対処法などをお伝えしました。
口座凍結の解除も調べてみると約2週間ですから、特別長いわけではありません。
マイナンバーカードのほうが長く待ちましたよ。








